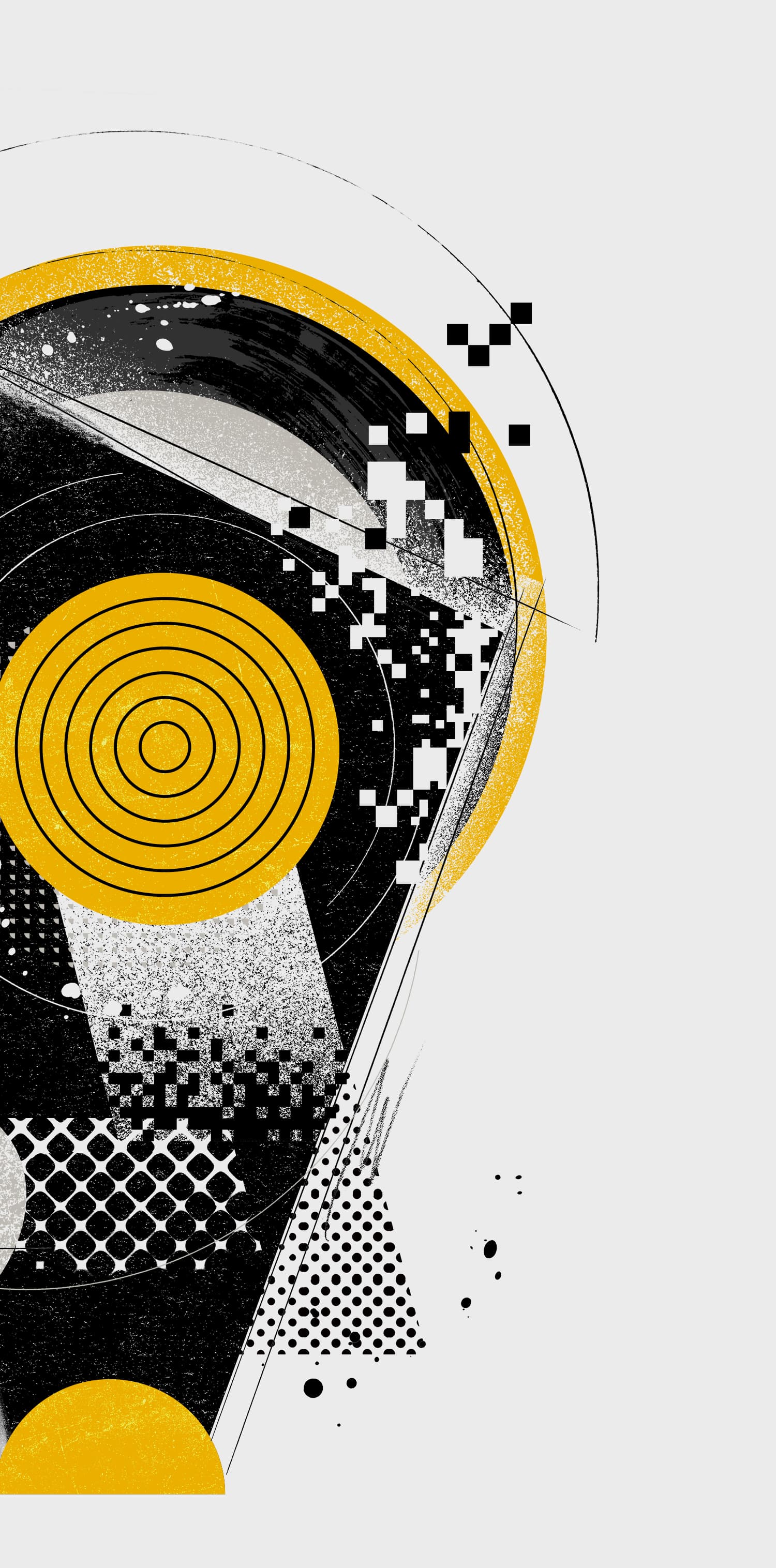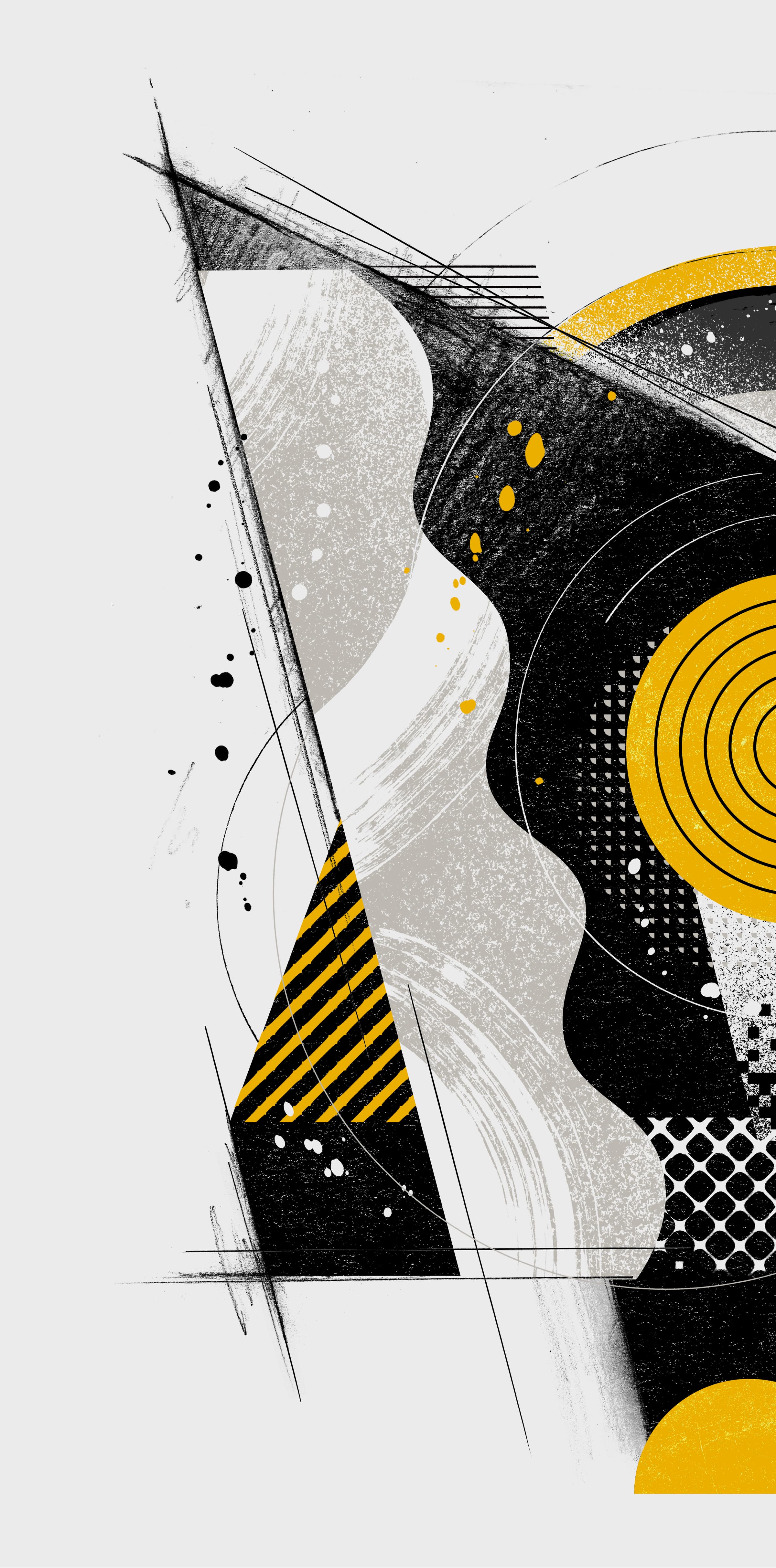下北沢はあらゆるカルチャーが交錯する街だが、とりわけ「音楽の街」として長年親しまれてきたことをご存知の読者も多いだろう。「下北沢Loft」のような老舗から、小さなミュージックバーを含めると、ライブハウスの数は実に30軒以上。そこでは数々の名演が生まれ、スピッツやBUMP OF CHICKENなどの国民的バンドも巣立っていった。当事者から見たライブ・シーンの貴重なエピソードをはじめ、7月7日より開幕する「第31回 下北沢音楽祭」にかける想いまで、人生の半分以上を下北沢で過ごしてきたという「CLUB Que」の代表、二位徳裕さんに話を聞いた。
ロックのライフスタイルを体現する場所
―94年のオープン以来、CLUB Queでは氣志團やUNISON SQUARE GARDENなど錚々たるアーティストを輩出してきました。元々はどんな構想が?
昔からイギリスの70年代後期のパンク・ロック~ニューウェイブが好きなんですが、スタンディングでワイワイやって、体をぶつけ合いながらライブを楽しんでいる写真に衝撃を受けて、日本にもこういうライブハウスがあったらいいなと思ったのが出発点ですね。特に欧米のロック・ミュージックは、ファッション、車、オートバイといった人間のライフスタイルや趣味がそのまま音楽に結び付いている。ステージに立つ時だけが本番じゃないんだぜ!という彼らのスタンスに感銘を受けて、ライブハウスに行く前も行った後も楽しんでもらえるような、そんなお店づくりを心がけています。

代表の二位徳裕さん。CLUB Queの公式YouTubeも自前で撮影・編集・運営している。
―既にバンド・シーンが活況だった新宿や渋谷ではなく、なぜ下北沢を選んだのでしょう。
単純に鉄道がクロスしていて新宿や渋谷に行きやすかったから、住む場所として下北を選んだことが発端だったのですが・・・。
仕事的には少し遡りますが、昔バンド活動の傍ら、田町の「インクスティック芝浦ファクトリー」(スタンディング形式のライブハウスの先駆け的存在、1989年に閉店)で働いていたんです。その後バンドで出演していた下北沢の代表的なライブハウス「屋根裏」(2015年に閉店)のブッキングを担当することになった。元々は「ロサンゼルス・アンチノック」っていう名前で超アマチュア向けのライブハウスだったんですが、渋谷の屋根裏(浜田省吾、THE BLUE HEARTS、RCサクセションなどを輩出)が86年に閉店することになり、そこのスタッフが流れてきたこともあって、「じゃあ『下北沢屋根裏』に変えちゃおう!」と。ホントは数年勤めたら音楽の仕事から足を洗おうと思ってたんですけど、当時屋根裏コンピCD作ったりで世話になっていたUK.PROJECTの遠藤幸一に誘われて、Queの店長兼ブッキングになり今に至る感じです。
―なるほど、当時の下北沢の音楽シーンについて聞かせていただけますか?
下北沢の屋根裏には、それこそ売れる前のMr.Childrenやスピッツが出ていましたね。あと、バンドマン同士の交流というか、飲みの文化がすごく盛んでした。六本木や渋谷でライブをやったら、打ち上げの二次会・三次会は必ず下北沢に流れる……みたいな。ただ、下北沢が「音楽の街」として知られるようになった起爆剤は、90年以降ライブハウスが増えて、「新宿Loft」などを運営するLoftが91年に「下北沢SHELTER」をつくったことでしょうね。そこから93年に「CLUB251」、94年に「GARAGE」と「CLUB Que」が立て続けにオープンして。それまでに屋根裏で育ったTHEE MICHELLE GUN ELEPHANT(以下、TMGE)やHi-STANDARDなどエネルギーを蓄えてきた次世代のミュージシャンたちの活躍に煽られて、新宿・渋谷あたりのベテラン勢も続々と下北沢に流れ着いたわけです。当時のライブハウスのイメージって今より遥かに悪かったんですが、下北沢は良い意味で呑気な街でもあるので、ライブハウスの物件が借りやすかったのかな(笑)。僕らも上京したばかりの頃はよく飲み屋のマスターやビリヤード場なんかの先輩達に可愛がってもらってましたし、打ち解けたら活動域が二乗で増える街ですよね。
自分を本気にさせてくれたバンド
―長年ライブハウスでたくさんのミュージシャンを見てきたわけですが、人生観を変えられるような出来事はありましたか?
THE COLTSや氣志團や沢山有りますが、やっぱり、真心ブラザーズの二人にはガツンとやられましたね。なんとな〜くでこの仕事を始めて、自らの音楽をやるための場繋ぎ的に続けてきたんですけど、特に桜井秀俊くんが真心以外でやってる「びっくりしたな、もう」っていうバンドはかつて見たことも聞いたこともない変ちくりんなバンド。ただ、音楽的にも、キャラクター的にも、動員力も、別格だったんですよ。メンバーみんな早稲田大学出身で頭も良いんですが、何よりも奇抜という意味で“パンク”を感じたんですね。「こういう人たちを応援したい」っていう想いが、僕を本気にさせてくれた。そうこうしてるうちに、怒髪天が北海道から上京してきて、TMGEが出てきて、Hi-STANDARDの横山健くんが屋根裏のバイトとして入ってきて……。今振り返ると、音楽シーンのキーマンが既に下北沢には集結していた気がします。それに、駆け出しのバンドと既に人気のあるバンドが音楽ジャンルを超えて同じライブでブッキングされることもあったので、意外性があるのも下北沢の面白さですね。

90年代当時のエピソードを語る二位さん。「とにかく無我夢中で走ってきました(笑)」。
―すごい時代ですね(笑)。ブッキングの妙というか、その意外性が後の「FUJI ROCK FESTIVAL」や「RISING SUN ROCK FESTIVAL」のようなフェスティバルのラインナップにも影響を与えているのかも。
でも、大元を辿ると「NEW YEARS WORLD ROCK FESTIVAL」(※内田裕也主催で1973年から毎年開催されている年越し音楽イベント。2000年には下北沢・本多劇場が会場に選ばれた)の存在が大きかったんだと思います。それの影響なのか、ミュージシャンたちが大晦日の下北沢に集まり、各バンドライブハウスを1日で5~6箇所も回って、そのまま元旦の朝まで過ごして夕方まで飲む……みたいな(笑)。誇張抜きに、それが今のサーキット・イベント(ライブハウスや飲食店を複数箇所回って開催されるイベント)の原点になってる部分はあると思います。バンドにとっても機材を持って何箇所回れるか?がある種のステータスでしたし、スケジュールを上手くこなすことの喜びや達成感はもちろん、何よりタフになれますよね。
―ライブハウスとして新しいプロジェクトや、挑戦をやってやろうという気持ちもあった?
いやいや、そんなカッコいいもんじゃないですよ。とにかく盛り上げようぜ!って無我夢中にやってただけで。階段を一歩ずつ上がって、その頂上に何が見えるのかなんて全くわからないですから(笑)。ただ、こうしてこの仕事を続けてこられているのも、日々新しい出会いと刺激があるからです。今日から3ヶ月後にあのバンドのライブが決まったから、どこよりも盛り上げるために、3ヶ月間は毎日頑張らなきゃいけないことの連続。それが今日まで続いてきちゃったというか……。

ライブハウスの閉鎖的なイメージを払拭したい
―Queが協力している「第31回 下北沢音楽祭」も、今年は有観客で完全復活ですね。
以前僕が担当していたのは駅前ケージ付近のステージだったんですけど、それが昭和信用金庫(らいぶはうす SHINKIN PARKING)に移ります。たまたま知り合ったカナコーという会社の会長がステージトラックや旧いギターや機材をたくさん持ってて、僕も好きなハーレーダビッドソンに乗っている人だったのですぐに意気投合しまして(笑)。そこの会社が昭和信金の駐車場にステージトラックを用意してくれることになっています。街中なんで大きな音は出せないけれど、逆にそれが僕らにとっては新しいチャレンジで。ロックンロール・バンドの人たちでも、小さい音でこんなに楽しませられるんだよって。ライブハウスってまだまだ閉鎖的なイメージが根強いですから、下北沢音楽祭を通じて音楽の間口を広げることができたら嬉しいです。
―下北沢音楽祭には、モデルとなっているイベントがあるんでしょうか?
昔、一度だけ日本音楽制作者連盟の視察でパリに行かせてもらって、「Fête de la Musique(音楽の日)」という音楽祭を体験したんですが、個人的にはかなりインスパイアされてますね。82年に誕生した歴史のある音楽祭で、イベンター、プロモーター、レコードショップ、そしてウチみたいなライブハウスが一堂に会して、街ぐるみでお祭りをつくっていく。それこそストリートで勝手に演奏をおっぱじめる人もいれば、マンションのベランダから法螺貝で参加する人もいたり、とにかく自由(笑)。2階建てバスに機材を組んで走らせたり、寺院の階段でオーケストラを組んだり、それを受け入れている住民の懐の深さにも感動しました。そういう光景を目の当たりにして、「いつかこれを下北沢でやれたらいいなあ」っていう想いが漠然とあったのかもしれません。
―2年前に比べるとライブやフェスも通常営業に戻りつつありますが、下北沢の音楽シーンはコロナ禍の前後でどのように変化しましたか。
まあ、がむしゃらにやってると違いも何もわからない感じですが、ふるいに掛けられた感じはありますよね。(エンタメ全般が)やりたくてしょうがない人しか続けられない仕事になったというか、「覚悟」を決めないとやれないところまで立ち返った。そういう意味ではポジティブに受け止めています。ただ、それってコロナというよりも「社会」によって変わってきたという実感があって。教育、街の環境、仕事の環境、人々の価値観……。たとえば、タトゥーを入れたり金髪にすることって、昔なら職を失うなど相当な覚悟が必要だったじゃないですか?それが現代はわりとカジュアルに、敷居が低くなってきたぶん、覚悟を決めてやっていた人たちに比べるとパッションが弱いなと感じてしまうことも多々あって。でもコロナ禍だろうが何だろうが、変化していく社会の価値観の中でもやり方を工夫して、本質的な部分で生きる道を模索できた人たちはちゃんと生き残ってますよね。
―下北沢は大きな変化の時を迎えていますが、この街だからこそやってみたい実験/挑戦はありますか?
実は、映画を撮りたいんですよ。2003年にも一度『Colors of Life』っていう作品を撮っているんですけど、この6月に朝のTV番組「スッキリ」でMCしてた怒髪天の増子直純と宍戸留美ちゃんが当時の下北沢駅の階段を降りながら「この駅も10年後になくなるんだよね」って語る印象的なシーンがあって。だから20年後バージョンでは「この街も変わっちゃったねぇ」って言うシーンを絶対に撮りたい(笑)。あと、もうすぐQueが30周年を迎えるんで、その際は井ノ頭線の電車内でライブやらせてもらえませんか?

Club Queのステージ前にて。取材当日にリハーサル中だった出演者とも親しげに会話していた。
―最後に、未来の下北沢に期待していることは?
日本中はもちろん、世界中で下北沢にしかないもの……というのが絶対にある街なので、そこは大事にしてほしいなって思います。下北沢は他の都市や街に比べて再開発がゆるやかだったので、お金はないけど勢いだけはある若者たちが安値で物件を借りられたんですよね。でもそのおかげで、わざわざこの街に来たくなる個性的なお店が立ち並んでいることが面白いし、独特な雰囲気を醸し出している。そんな「スキマ」というか、余白、寛容さを失わずに成長してくれたら言うことなしですよ。あと個人的には、「珉亭」(1964年創業の中華料理店)がずっと残っててくれたらいいですね!店も、働いてる人たちも、そのまんま文化財みたいなもんですから(笑)。
―下北沢音楽祭の情報はこちらー
https://shimokita-fes.com/31th/