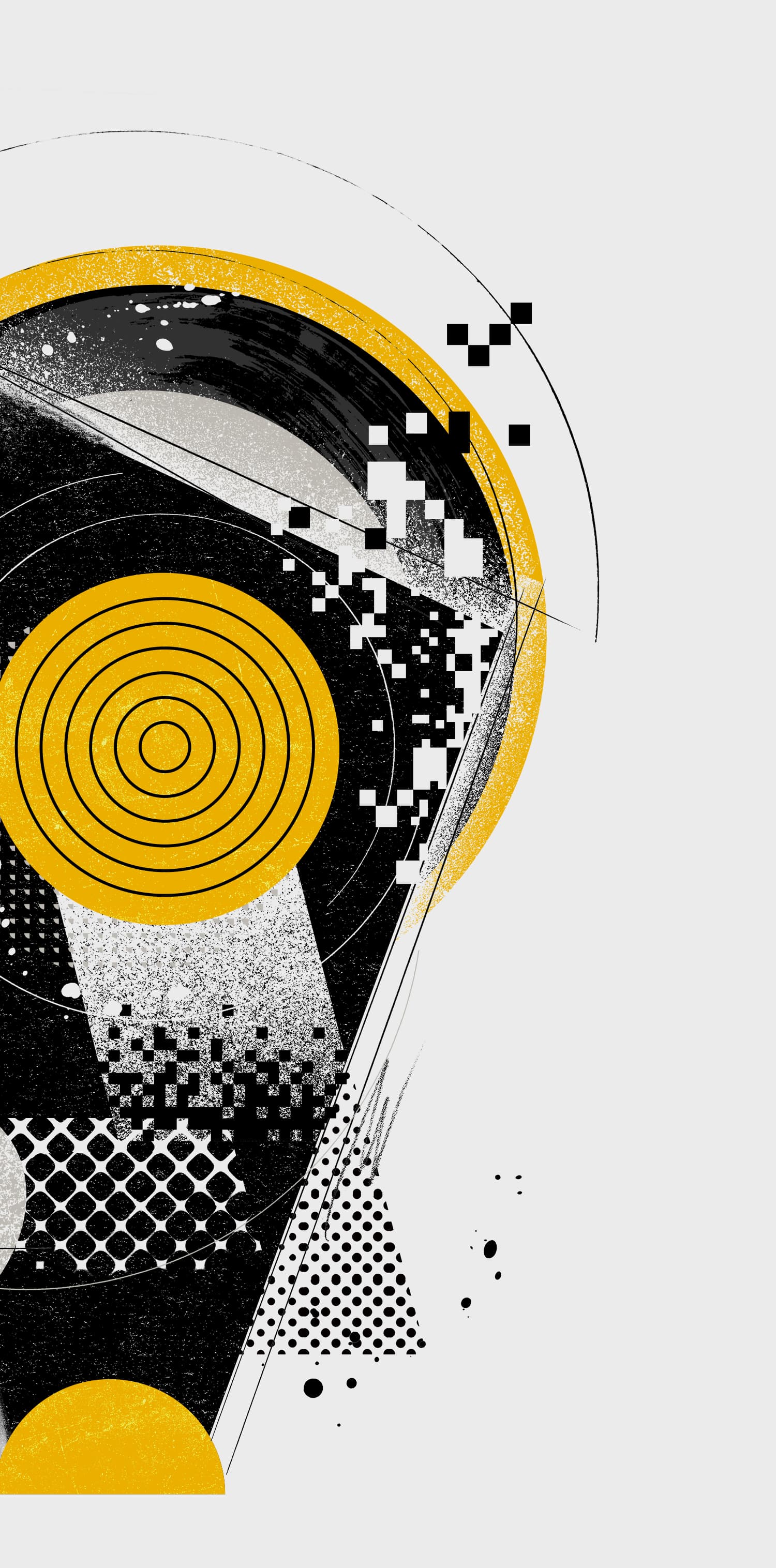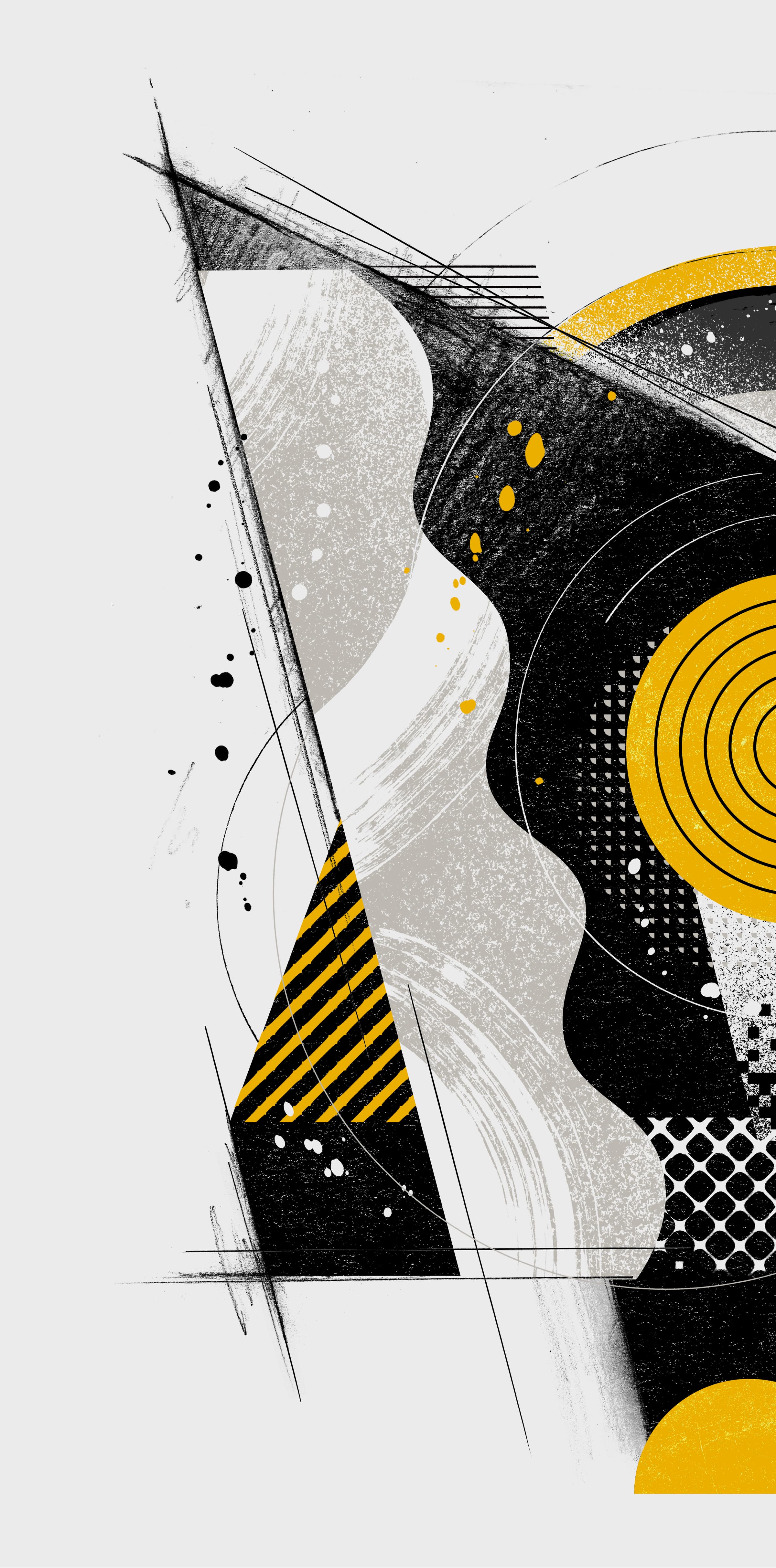総勢80名以上の高校生、大学生、社会人がともに暮らし、学ぶSHIMOKITA COLLEGE。レジデンシャル・カレッジとして2020年末に下北線路街に開業して以来、世代や専門の異なる学び手が互いの経験を持ち寄り、学び合うことで、新たなプロジェクトも続々と誕生しているという。なぜ下北沢の街で、このような場を開いたのか。共同運営を行う3社(小田急電鉄株式会社の橋本崇さん、UDS株式会社の三浦宗晃さん、HLAB Inc.の小林亮介さん)に、立ち上げに至るまでのストーリーや街×場×学びの掛け合わせがもたらす可能性について語ってもらった
街づくり、場づくり、教育づくりのプロが集結
—最初に、お三方のSHIMOKITA COLLEGEでの役割を教えてください。
橋本:私が主に担当しているのは、不動産やまちづくりの部分です。小田急電鉄ではこの数年間、下北沢エリアを「下北線路街」として13施設の計画を進めてきました。その中で、高校生や大学生との接点を増やす施設として、SHIMOKITA COLLEGEも手掛けています。

小田急電鉄株式会社 まちづくり事業本部 エリア事業創造部 課長の橋本崇さん
三浦:私が所属するUDSは、元々コーポラティブハウス(家を建てたい人が集まり、自分たちでつくる集合住宅)のコーディネートを行う事業からスタートし、それ以外にもシェアハウスや食堂事業など、集合住宅施設の企画から設計、運営までを多岐にわたって手がけてきました。ここでは事業企画と空間設計、開業後は主に不動産管理と食堂運営を担当しています。

UDS株式会社 事業企画部 システムデザインユニット ゼネラルマネージャーの三浦宗晃さん
小林:僕が代表理事を務めるHLABは、多様な学びの体験、空間、コミュニティのデザインを行う会社です。これまでも高校生向けの合宿型サマースクール事業を中心に手がけてきましたが、ここではレジデンシャル・カレッジとしての長期的な教育プログラム設計と運営を担当しています。

HLAB Inc.代表理事の小林亮介さん(オンラインでのご参加・編集部撮影)
—企画の部分は、みなさんで一緒に考えていったということでしょうか?
橋本:はい。誰がトップということもなく、三者でガンガン意見を出し合って、コンセプトやビジョンを決めていきましたね。
三浦:僕らUDSはいかに学びを促す空間をデザインできるか、小林さんたちHLABはユーザーのニーズを汲みながらいかに学びに反映させるか、そして橋本さんたち小田急電鉄はいかに不動産への投資を回収していくか、三者三様の観点を統一させ、動かしていく必要がありましたからね。
小林:橋本さんも三浦さんも、スタートアップである僕らの意見をしっかり聞いてくださって、できないことも「どうやったら実現できるだろう」と一緒に考え、議論してくれました。本当にいいチームでしたね。
—みなさんがワクワクできるプロジェクトだったのですね。初めからそのようなチームワークがあったのですか?
橋本:繋がりは以前からありました。元々「学生寮をつくりたい」という構想は2016年からあって、社内コンペで提案したところ、新規事業として実現できることになったのです。そこで2018年に小田急のグループ会社であるUDSさんに声を掛け、湘南台に「NODE GROWTH」という食事付き学生寮を立ち上げたのが始まりでした。
三浦:シェアハウスのコミュニティのある住宅事業や、学生食堂事業はそれまでも運営してきましたが、両者を組み合わせた食事付き学生寮というフォーマット自体は、UDSとしても初めての挑戦でした。単なる食事付き学生寮をつくりたいわけではなく、住環境における学びのOS的な部分を模索する必要があって。一緒にやってくれるパートナーを探していた時に、小林さんに出会いました。
小林:そこから、僕たちも少しずつ関わりを深めていきましたね。
橋本:小林さんが語ってくれた、学生時代ハーバード大学の学生寮に住み、その実体験からどのような学びや発見があったのかという話がすごく面白くて。そこから海外の名門校で一般的に行われている居住型の教育を日本で実現したいという考えをシェアしてもらうなかで、私たちも日本だからできるレジデンシャル・カレッジのあり方を、より身近に考えていくことができました。

学びの90%以上が寮にあった、ハーバードでの寮体験
—ハーバードの学生寮でどのような体験をしたのか、気になります。
小林:ハーバード大学では、1年生はほぼ全員が寮に入ります。また、2年生以降も多くの学生が寮に残り、学校の中で暮らしていきます。全寮制の学校は、日本だとあまり馴染みがないかもしれませんが、「ハリー・ポッター」で描かれるホグワーツ魔法魔術学校の寮がイメージしやすいかもしれませんね。ホグワーツは寮が4つに別れていますが、ハーバードはなんと12個。どの寮になるかは抽選で決まるので、学生は自分では寮を選べません。ただし誰と一緒に寮に入るかは選べるので、8人ぐらいでチームを組んで抽選に挑みます。そうして寮に入ると、4学年合わせ400人ほどの寮生がいて、彼らとの共同生活が始まります。
—設定を聞くだけでもワクワクしますね!
小林:ユニークですよね。寮自体が必ず食堂を通らないと自分の部屋まで行けない設計で、なおかつ食費も先払い制なので、みんな外食をせずに寮で食べるようになります。しかも食堂では、24時間コーヒーが無料で飲める。すると、みんながそこに集まりだすわけですね。
例えば図書館で期末試験の勉強をしようと外に出ようとしたら、食堂で無駄話をしている6人ぐらいに掴って、専門も夢も年齢もバラバラの人たちとたわいもない話をする。そんな光景が日常茶飯事になります。その時いた彼らは医者やコンピュータ・サイエンティスト、何千億円という会社を経営する起業家もいれば、音楽家になっている人もいて。このように、一見なんでもないような時間が、人生を探索するプロセスになっている。僕自身も、この体験がなければ全く違う道に行く人同士でリスペクトする気持ちも培われなかったでしょうし、「こんな人生の歩み方もあるんだ」という気づきや、「将来こういうことがやりたいよね」といった共創の話が発生する機会も少なかったと思います。それは僕だけではありません。他の卒業生からも「大学の学びの90%以上が寮にあった」という話が口々に出てきます。
—学生時代、さまざまな人と接することで、広い視野でものごとを考えられるようになる。とてもいいと感じますが、日本ではそのような機会は少ないと感じます。
橋本:そうですね。日本の状況を見ていくと、街にはさまざまな学校があるにもかかわらず、それぞれに接点がなく、不動産としてもうまく街と連携できていません。
小林:今の日本では、官民連携や多様性などに力を入れているものの、積み重ねた信頼関係の中でいろんなアイデアが出て、本来起こり得なかったコラボレーションが生まれ、社会にインパクトを与えていくといった結果までに至っていないのが現状です。この抜け落ちた穴を埋めるピースが、まさにこの居住型の教育なのではないかと我々は考えていて。それを橋本さんや三浦さんに投げかけ、議論していった結果、大学の中に閉じず、街の中でレジデンシャル・カレッジを運営していくことで、東京・下北沢という多様な街のリソースをより活かせるかもしれないという方針に至りました。
交流を生み出す、徹底した仕組みづくり。SHIMOKITA COLLEGEのハードとOS
―多様な人の交流を促す場にするために、工夫したことを教えてください。
三浦:ハード面は、僕らUDSが日本で培ってきた共同住宅づくりのノウハウと、小林さんが集めてきた世界中の寮のリサーチデータを掛け合わせ、具体的な設計に落とし込んでいきました。SHIMOKITA COLLEGEも、エントランスを入ってすぐに食堂を置き、そこを必ず通って自分の部屋に行く構成としました。
小林:さらにフリクションという、ユーザーに心理的な負担をかけない設計にもこだわっています。例えばエレベーター前には、壁やドアを設置せず、フロアごとにしつらえの異なるラウンジを設置することで、心理的なハードルを下げ、人がたまりやすくなるようにしています。
三浦:また、ランドリーも1ヶ所に集約し、待ち時間にゆったりできる大きめの応接間をつくりました。そうすることで全館から洗濯しに集まってきたカレッジ生が、自然と顔を合わせることになり、偶発的な交流を促します。当初はなかったギターやキーボードをカレッジ生がもちこんで、夜な夜なセッションを行ったりしているようです(笑)。
小林:アメリカだとFireside Chatというカジュアルな形式の座談会が開かれることも多いので、「火のそばで安心感を得ながら語らうために、暖炉が欲しいです」という要望も出しました。そういった無茶な提案にも応えていただきました。

(画像提供:UDS)
―施設というハード面とユーザーを繋ぐOSの部分はどのように考えてつくったのでしょうか?
小林:例えば、レジデンシャル・カレッジの中に住みながら、入居者の面倒を見てくれるチューター的存在を、大学院生ではなく社会人に入ってもらったり、アメリカと同じ街の規模間でレジデンシャル・カレッジのあり方を考えてみたり。海外の寮のスタイルをそのまま持ってくるのではなく、東京という街にあることを活かしながら、日本の大学にはない内容を考えていきました。
三浦:この2年間はコロナ禍という厳しい状況だったからこそ、目指すべきオペレーションや住環境と教育のあり方を根本から問い直すことができた点も、結果的には良かったと思います。また、検索サイトから部屋を絞り込み、カタログスペックや格好よさで住む場所を決めるのではなく、「こういう体験をしたいから、こういう住まいを選ぶ」というような考え方の人に受け入れられるように伝えています。
小林:寮生活は自分とは異なる生活スタイルや考え方をもつ人たちと過ごすものですからね。なにかトラブルが起きた時も、お互いがどう変化し、どう解決していくか、周囲にどう貢献していくかを考えられるようなマインドセットを身につけることを期待して来てもらうことが重要で。ですから、入居の際も書類と面接による選抜審査のプロセスを設け、みんながオープンマインドでいられる環境を確保しています。

画像提供:HLAB
―とはいえ、高校生が大学生や社会人に話しかけることは、日本ではなかなかハードルが高いですよね。
小林:そのためにも、1週間に1回ほど誰かに話しかけに行くというルールを設定し、Slackなどのコミュニケーションツールでも週に2回誰かとマッチさせるような場を設けています。そういうことが当たり前になると、カルチャーとなり、みんなが気兼ねなく話せるようになるんですよね。また、より多様なプレーヤーたちと会う機会を増やすため、下北沢で活躍している面白い大人たちにも来ていただいています。昨年はサッカーの日本代表コーチを務めた岡田武史さんがここに訪れ、暖炉の前でコーヒーを片手にお話ししていただきました。そのくらい近い距離感で大人たちと話すことも、ある意味トレーニングになるんですよね。このように、共同生活の場を最大限に活用しながらトライできるようにしています。
橋本:下北沢にはいろいろな人たちが集まるフィールドがありますし、私たちもそんな人たちとのつながりがあるので、レジデンシャル・カレッジの入居者間だけでなく、街に関わる人を引き合わせることができます。そうすることで、小林さんがハーバードで体験したような「こんな人もいるんだ」という発見も生まれていくでしょう。ゆくゆくは、街ぐるみでSHIMOKITA COLLEGEを育てていくような、日本独自のあり方を構築できたらと思っています。
―これまで、寮生と運営が一緒に立ち上げたプロジェクトで、印象的だった企画はありますか?
小林:最近だと、UDSさんにご協力いただいた「シモキタご縁日 2022」や小田急電鉄さん主催・作家の辻仁成氏創設の「アート&デザイン新世代賞」でしょうか。他にも、冊子の制作やハロウィン飾りの制作なども行って来ました。立ち上がったプロジェクトは基本的には寮生が主体となって行いますが、最後までやり遂げられるようチューターがサポートしながら進めていますね。

「シモキタご縁日 2022」の様子(画像提供:HLAB)
三浦:こういった経験を通して下北沢が思い出の街となり、カレッジがここにあり続けることでいろんな人が遊びに行きたいと思えるような好循環が生まれてくるといいですよね。下北沢にはそういった多層的なコミュニティのレイヤーをつくれるポテンシャルがあると思っています。
“シモキタ”だからつくることができる、街の未来
―SHIMOKITA COLLEGEの立ち上げや運営を通して気づいた、下北沢の魅力を教えてください。
橋本:私は下北沢で5年間まちづくりをやってきたのですが、下北沢駅周辺は南北で生活圏がハッキリと分かれ、「下北沢という地名で一緒にしないでくれ」と敬遠する人がいるほど、分断されたエリアでした。でもある時気づいたんです、みんな「シモキタ」という言葉は共通して使うんだな、と。その違いは何かと考えた時に、地域の人たちが思い思いに好きなことをしているとき、分断を超えてみんなを繋げる言葉として使われていることに気がつきました。そして反対をしていた方々と、「シモキタ」という言葉を通して話し合ったことで、まちづくりに参加できないことから怒っていたことに気づくことができました。その時はじめて、老若男女みんなが下北沢で繋がるビジョンが見えたんですよね。昔から下北沢で遊び尽くしてきた、街を支えるシニアの人たちのマインドは、若者にも通じるものがある。だからこそ、多様性があたりまえにある下北沢の文化の中で、老若男女問わずそれぞれが本当に好きなことをしている状態を生み出すために、我々も支援型の再開発に切り替えました。
最近も、意見を戦わせながら仲良く飲んでいる下北沢の人たちをよく見かけます。それはきっと、人格を否定せず、意見の交換をしようとする意識が根本にあるからでしょう。そんな昔からある下北沢特有の文化は、これからの多様性の時代へと変わる中で、より輝く存在になるはずです。
小林:多様であることに誇りを持っている街であるということは、外部の人間からも感じられます。それに実際街の中に入ってきてみると、僕たちもまさにそういう文化が根付いていると実感できて、レジデンシャル・カレッジで築いているカルチャーとも親和性があると感じています。
―事業の観点から、レジデンシャル・カレッジで実験していきたいことはありますか?
橋本:レジデンシャル・カレッジは、基本的に親御さんからお金をいただいて運営されています。しかし、子どもの学びのコストを親が全部背負うのはおかしいと私たちは考えていて。新しい社会に変えていく上で、若者の成長を支えることは必要不可欠。その意識をみんなが持つことで、企業から協賛を集めたり、行政からの支援を得たりするなど、もっと社会的に取り組むことができると考えています。つまりtoCだけではなく、toBで寮の運営をしていきたいということですね。
小林:おっしゃる通り、これはまさに教育のビジネスモデルをつくる話でもあります。僕がハーバードにほぼ無料で通えたのも、ビル・ゲイツのように成功したOBたちが、莫大なお金を寄付することで、基金の運用益が学生に降ってくるというモデルがあったからこそ。そしてなぜそれができているかと紐解くと、やはり4年間の寮生活で濃密な時間を過ごしたことで、圧倒的な帰属意識が植え付けられ、さらにその素晴らしい体験を次世代にも引き継ぎ、新たな成功者を生み出したいという思いが根底にあるからでしょう。
三浦:このような短期的投資回収ではなく長期的視点で複合的なインパクトを有んでいくようなシステムは、日本の鉄道会社が20世紀初頭から行ってきたことだと思います。線路を引いて、住宅街をつくり、郊外には学校も建て、帰属意識を路線に持ってもらった上で、大人になってからその街に戻り、働いたり、マイホームを買ったりしてもらう。こういった長期的な事業観点を持って、レジデンシャル・カレッジも発展させていきたいですね。
―最後に、それぞれがこれから取り組んでいきたいことや夢について、一言ずつお願いします。
小林:一緒に住んで学ぶ際に、多様性をどう活かすのかという課題に、引き続き取り組んでいきたいですね。今後、日本は移民を受け入れなければいけなくなるでしょうし、世代間のバランスもいびつになってくるでしょう。だからこそ自分と違う人と、壁を飛び越えた交流が重要になってくる。そういった考え方をこの居住型教育を通して広めていけたらと思います。
三浦:SHIMOKITA COLLEGEをきっかけに、全国各地から「うちの地元に作ってくれないか」というオファーをいただいているので、今後も色々なところにカレッジを作っていきたいですね。そして新しい〇〇カレッジを増やしていきながら、異なるエリアのカレッジ生同士をどんどん交流させていけると面白いなと思っています。
橋本:私の場合は極端かもしれないですが、子どもが中高校生になったら寮に入れる子育てスタイルを提案していきたいですね。そうすることで、子どもの自立性が培われ、親子の関係性もほどよく保てる。不動産的にもコンパクトなマンションで良くなり、老後に部屋が余るということもなくなりますし、トータル2000万円ほど浮くので、そのお金を教育に投資できる。こういう子どもの教育に投資することがあたりまえの社会になっていったら、面白いですよね。