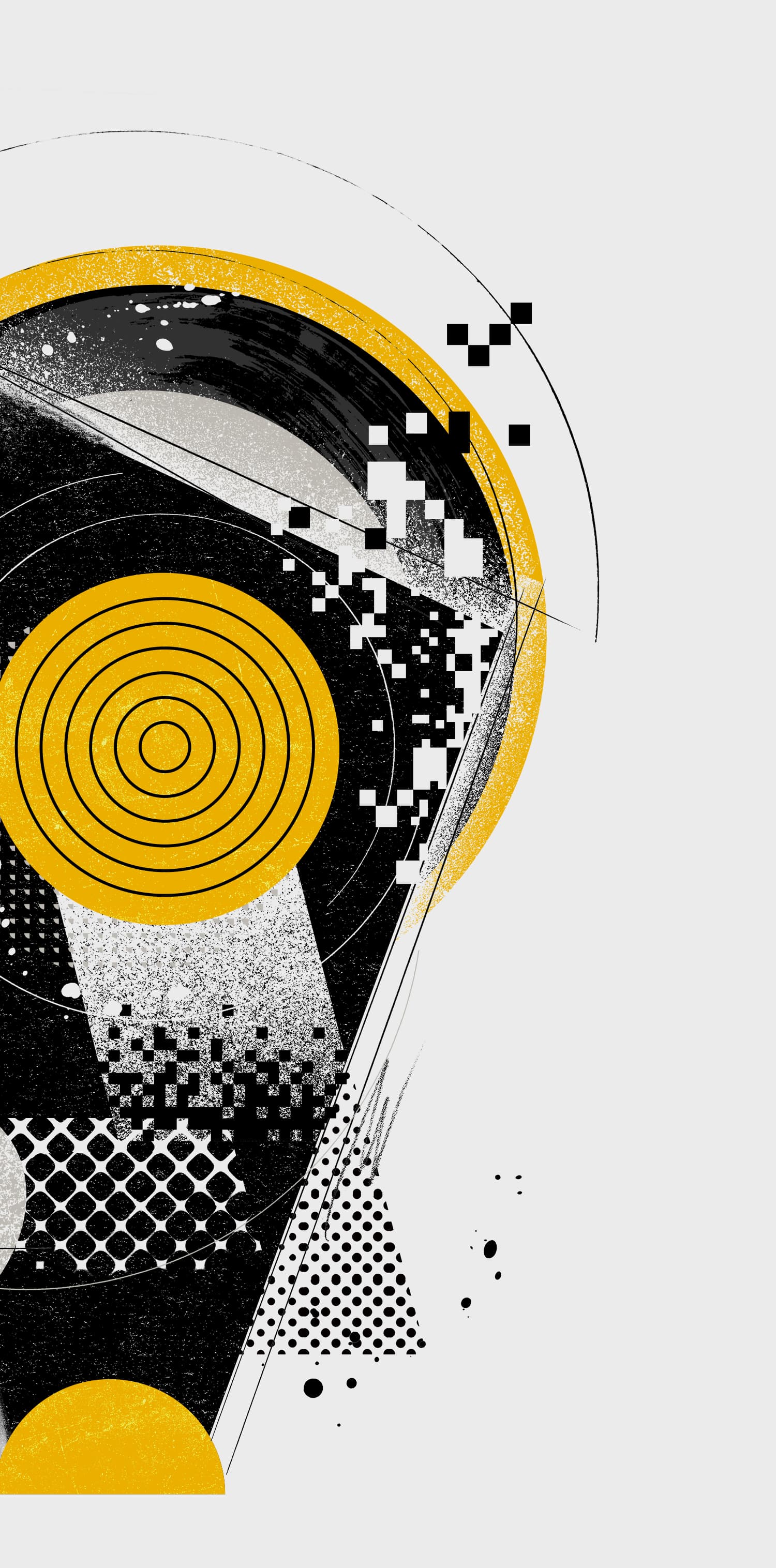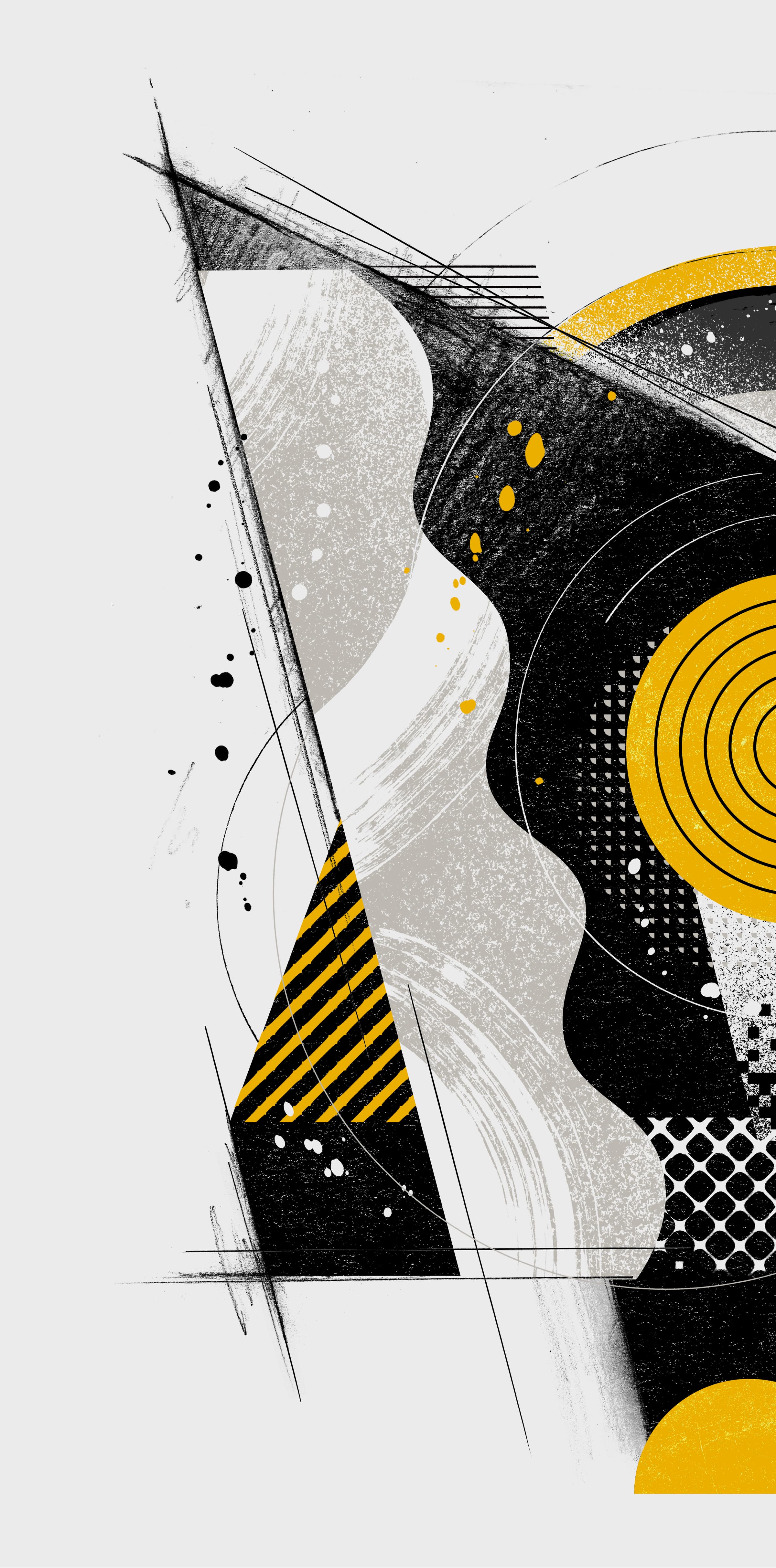2023年10月12日(木)、下北沢・BONUS TRUCKにVHS喫茶『TAN PEN TON』がオープンした。2022年に設立された映画会社「NOTHING NEW」が手がけるカフェ&バーで、目指すのは“ショートフィルムのちいさな発信拠点”となること。
『TAN PEN TON』を立ち上げたのは、映像業界で活躍する林健太郎さんと鈴木健太さんだ。
林さんは学生時代からインディペンデント映画の制作に携わり、現在もプロデューサーとして映画作りに関わっている。鈴木さんは10代から映像・アニメ制作を開始し、現在は広告会社で様々なクリエイティブを手掛けている。映像業界の最先端を走るふたりが、なぜ「ショートフィルム」に注目したのか。そしてすでに生産終了した「VHS」に感じている可能性とはなにか。下北沢を場づくりの拠点に選んだふたりに、『TAN PEN TON』が描く想いを聞いた。
同級生の作品で感じた「映画業界の不条理」
—林さんと鈴木さんが、一緒に活動するようになったきっかけを教えてください。
林:コロナ禍に自分が立ち上げた、オンラインで創作をする「劇団ノーミーツ」がきっかけです。最初は短編の作品をSNSに上げていたんですが、「長編の生配信公演を有料でやろう」と、それまでよりスケールの大きな挑戦をすることになって。そのタイミングで、スズケン(鈴木さん)に声をかけました。コロナ前に1度しか会ったことのないくらいの関係だったんですけど、作っているクリエイティブがすごく好きだったんです。だから、はじまりはリモートだったんですよ。

林健太郎さん。コロナ禍に生まれた「劇団ノーミーツ」発足メンバー。大手映画会社での企画開発や劇場勤務を経て、現在は映画プロデューサーとして活躍
鈴木:コロナ禍でエンターテインメントが「不要不急」と言われる状況は、作り手や演者にとってものすごく逆境でした。ノーミーツもSNSでバズって終わり、ではなくて、興行として盛り上がれば、仮にコロナがずっと続いても作り手や演者が創作で生きていくための“一種の選択肢”になるかもしれないと思ったんです。最初は「予告編作ってよ」くらいの感じの打診だったんですけど、僕も燃えてしまって(笑)。ノーミーツという林くんを中心とした素晴らしいアクションに、より大きな妄想をのっけた僕の提案を快く受け入れてくれて、一緒にオリジナル作品を作るようになりました。

鈴木健太さん。CMの企画からミュージックビデオの監督、プロジェクトの立ち上げまで、手がけるクリエイティブは幅広い。「劇団ノーミーツ」にはクリエイティブディレクターとして参加
—おふたりとも活動のメインテーマに「映画」や「映像」があると思います。この分野にのめり込むようになったのはなぜですか?
林:僕が最初に映画を好きになったのは、高校3年生です。クラスメイトに「ショートフィルムをつくるから衣装を提供してほしい」と言われて、柔道着を貸したんですよ。数か月後に「完成したから観て」と言われた作品が、めちゃくちゃ面白くて。で、「同級生がつくったショートフィルムがこんなに面白いのに、映画館で観られるのは大作だけ」だったことに気付いたんです。商業作品も大好きなんですけど、小さな作品ももっと世の中に出て良い。小規模な作品だったとしても、観て心を動かされる瞬間はある……自然と、尖った作品をつくる人や若い監督に打席が無いのは「あまりにも不条理なんじゃないか」という感情が生まれたんです。当時から今にいたるまで「規模の大小を問わず面白い作品をつくりたい」という想いは変わらなくて、そのままここにたどり着いたという感じですね。
鈴木:僕は子供の頃からコミュニケーションに苦手意識がありました。『スターウォーズ』や海外のアニメーション作品を観たのがきっかけで「自分でもつくってみたい」と思い、小3のとき家にあったiMacで作品をつくってネットに上げるようになったんですよ。映像をつくることが「人に何かを伝える」自分自身のコミュニケーションツールになっていきました。小6で『デジタル・スタジアム』(NHK)という番組に応募したら、明和電機の土佐信道さんという方に「面白い」と言っていただけて。映画など映像を観るのも好きだけど、作り手としてそこに携わりたい。そういう想いが今に繋がっていますね。
カオスだけどスタイリッシュ……BONUS TRACKではじまる実験
—VHS喫茶『TAN PEN TON』は、2022年に立ち上げた映画会社NOTHING NEWが手がける事業ですね。どんな想いで映画の会社をつくったのでしょうか?
林:コロナ禍に入る前、スズケンと出会ったときに「いつか一緒に映画に挑戦したい」という会話をしていたんです。それがやっと実現した、という感じですね。コロナ禍でスズケンと一緒にノーミーツの活動のほか、ストーリーゲームレーベル『POLARIS』でボードゲーム開発を手掛けたんですが、それらはいずれも「コロナ禍や業界の固定観念という逆境のなか、どうやって新しい創作の在り方を追求するか」が活動の核で。既存とは異なるやり方で一緒に作品づくりやチームづくりに挑戦する経験を経て、今あらためて「映画をやりたい」と。

林さんと鈴木さんが初めてタッグを組んだ作品。「劇団ノーミーツ」旗揚げ公演『門外不出モラトリアム』は、全員一度も会わずにオンラインで制作された。文化庁メディア芸術祭 優秀賞受賞。

ストーリーゲームレーベル「POLARIS」による、マーダーミステリー『RED LINE』。吸血鬼と人間が対立した世界が舞台のボードゲームを作り、ゲームマーケットで完売。
鈴木:「ついにやるか」という感じです(笑)。林君って、現状への疑問や業界の閉塞感みたいなものに対して「本質的にどう取り組んだらいいんだろう」ということをかなり根底から考えるんですよ。そのうえでポジティブに「良いものを作りたい」という気持ちもある。課題のまま終わらせず行動する林君にはいつも感化されています。長年話していく中で「映画業界はどうなっていったら良いのか?新しい才能が活躍しやすくなる世界って?自分たちはそれに対してなにができるんだ?」という数々の問いが膨らんで「そろそろやるか」とはじめたのがこの会社です。
—林さんの活動の根底にある「若い世代の監督らに打席が無い業界の不条理」は、鈴木さんも共感するポイントなのでしょうか?
鈴木:「問題だよね」と言いつつ結局やらない人たちっていっぱいいるじゃないですか。そういうのを見飽きたし自分もいずれそうなるかもしれないので、その前に一旦「自分たちで動くしかない」という気持ちです。TAN PEN TONはその一手です。「やらないと始まらない」と思ってまずは場所を探していたとき、たまたまそのタイミングでBONUS TRACKのテナント募集を知り、応募しました。
—テナントに応募した方々がプレゼンをし、結果『TAN PEN TON』が選ばれたそうですね。なぜ自分たちが選ばれたのか、理由は聞いていますか?
林:詳細は聞いておりませんが、採択頂いた後に「スタートアップとして映画業界の構造に挑戦する姿勢を応援したい」と言っていただいたことは印象に残っています。これまでBONUS TRACKに自分達のようなタイプの会社が無かったこともあって、「新しい風が吹くんじゃないか?」と実験的な匂いを感じてもらえたのかもしれません。また、僕ら自身もBONUS TRACK、そして入っているテナントさんに対し、一度訪れた時から不思議ととてもシンパシーを感じていました。
鈴木:ひとつひとつのお店がコンセプトをしっかり持っていて、やりたいこと、目指してることがある。それがBONUS TRACKという一体感のある“街”になっている。生まれたばかりだけど唯一無二の魅力的な街で、そこに参加できるのは本当にありがたいです。

林:テナント募集の情報を知って、実際に足を運んだんですよ。各テナントがそれぞれ違う尖り方をしているのにエリアとして統一感がある……なんか、すごくカオスだけどスタイリッシュですよね。しかも下北沢には、何回もインディーズ映画を観に行ったK2さんやトリウッドさんもある。そういったところと連携し、下北沢を「映画の街」にしていきたいという想いが強くあります。
(参考)BONUS TRACKのテナント募集記事
https://note.com/bonustrack_skz/n/n07f99203eaf0
ショートフィルム×VHSで描く可能性
—『TAN PEN TON』はショートフィルムを切り口にしたお店ですよね。なぜ長編ではなく、ショートフィルムだったのでしょうか?
林:ショートフィルムは「可能性」だと思ってるんです。まだ身近な存在ではないこと自体が、映画業界の持つポテンシャルだなと。クリエイター目線だと、ショートフィルムって予算やキャリア的に長編を作れない人にとって“ひとつ目の名刺”になり得るものであり、本当に大きなチャンスを秘めている存在なんですよ。でもYouTubeに上げるだけでは観てもらえるか分からないし、発表する場がこれまではなかなか無かった。一方で、観る側の視点に立つと、短い作品が好まれる傾向が少しずつ出てきていて。つまり、短いけど深い体験ができるショートフィルムは、映画をコアに好きではない人にとっても受け入れやすく楽しんでもらえるチャンスがあると思うんです。だからこの店が、若い監督の面白い作品が見られるきっかけになれば良いなと思いますね。

グリーンをメインカラーに使っている『TAN PEN TON』。このグリーンは自然界に存在しないカラーで、既存の映画会社にはあまりないイメージが印象的
※画像元:https://motion-gallery.net/projects/TANPENTON
—作品を見られる場所を増やすという意味では、ネット上にプラットフォームをつくる方法もあったと思います。そのうえで、なぜ場所を持とうと思ったのでしょうか?
林:「作品との偶然の出会い」のようなコミュニケーションが生活から無くなってきていることに、もどかしさと、大きな可能性を感じているからです。オンラインで観られる作品が何百・何千とあって、レコメンドされたものをながら見する……それも良い体験なんですけど、例えばレンタルショップで内容も分からずジャケ借りした作品が「自分の生涯で大切な一作」になるみたいなことってあるじゃないですか。こういう視聴者と作品のコミュニケーションを愛する人、好きになる人はたくさんいるんじゃないかと思っていて、その可能性に賭けています。自分自身、『ゆれる(2006年・西川美和監督)』という作品をジャケ借りして、それが「生涯で大切な一作」になったんですよ。借りて失敗する経験もふくめ、自分で「選ぶ」ことって本当はもっと面白いんじゃないか?この店では、そんな提案がしたいと思ってます。

『TAN PEN TON』店内には、オリジナルデザインのシールを貼ったVHSがディスプレイされている。訪れた人は、ショートフィルムの“ジャケ借り”体験ができる
※画像元:https://x.com/TANPENTON/status/1707221009852740046?s=20
—ご自身の原体験が関係しているんですね。VHSにこだわったのはなぜでしょうか?
鈴木:今って、映像がどんどん“かたちの無いもの”になっていますよね。それゆえに、映像と人の距離感がゼロになっていって、作品に対する愛着のようなものも生まれにくくなっているような気がします。そういう時代だからこそ、映像をVHSという”モノ”に戻したらどうなるんだろう?って。そういう愉快犯的な実験です。テープって今は触れる機会も無いですし。生産が終了しているので、集めるのも大変なんですけど(笑)。
林:店に置いているビデオデッキは、僕の実家から持ってきたものです。実家で「昔どういうの観てたっけ」と掘り起こしたら、『ベイブ(1996年・クリス・ヌーナン監督)』のVHSが出てきたんですよ。値段を観たら、1万数千円して。つまり、昔は映画1本を再生・保有するのにそれだけの価値があったんですよね。時代の変遷によってどんどん安くなりましたけど、実家で『ベイブ』のVHSを見つけた時、「モノで映画を観ていた時代の記憶って、すごく強く残っているな」と思ったんです。小さい時のことなのに、印象的なシーンや見ているシチュエーションが、記憶の断片として残り続ける。その体験ってすごく愛おしいし、昔でしか成立し得ないものでもないのかなと。レコードやカセットが今復刻しているように、VHSが今またカルチャーになっても良いんじゃないかと思ってます。友達とワーッと話していても、デッキにVHSがガチャンと入ると、急に没入して干渉する空気に変わるじゃないですか。「集中してちゃんと観よう」という雰囲気に自然と変わっていく。プレオープンでそういう光景を見て、VHSの面白さを感じています。

『TAN PEN TON』を拠点に広がる妄想
—下北沢に拠点を置いてみて、印象はいかがですか?
林:カルチャーに対する熱量の高さを感じてます。まだプレオープン中(※取材は9月に実施)ですけど、「実はこの辺に住んでいるんだ」という同じ業界の方をはじめ、カルチャーに精通している人がたくさん訪れてくれて。「新しいことに挑戦したい」と考えている、同じにおいの人がどんどんお店に来てくれているんですよ。訪れた初対面の人同士で交流が生まれる様子を見ていると、次の一歩を仕掛けたい雰囲気が街にあることを感じてます。
鈴木:若い世代も海外の方も多く、あたらしいものに対して興味がある人の集まる場所だなと思います。完全な新入りですが受け入れてくれる空気感がこの街にはあって、こういう実験的なチャレンジも思いっきりできて本当にありがたいです。あとは、TAN PEN TONのTON(屯=たむろ)の意味を体現するように、いろんなバックグラウンドの方が心地よく集まれる場にしていきたいですね。

—本オープンしたら、さらにいろんな方が訪れてどんどんお店が進化していきそうですね。
鈴木:進化させていきたいですね。TAN PEN TONが映画の「ドアマン」的な存在となって、訪れた方にいろんな映画の楽しみ方や新しい才能に触れるきっかけになれば良いなと思います。まずは気にかけてもらうのがスタートなので、例えば写真家さんの個展だったり音楽イベントだったり、この場所をつかっていろんなことを仕掛けていきたいです。それから『TAN PEN TON』という雑誌を作るアイデアもメンバーの中ででていて。VHS喫茶は、興味をそそる入り口でしかなくて、お店を超えて「こういう作品が面白い」とか「こういう人がいるよ」ということを、僕らがオススメしていける小さな発信拠点にしていきたいですね。
林:どうやったら一緒に面白いことができるのか、いろんな方とお話したいと思ってるんです。だからこういったインタビューを通じて、新しいコラボが生まれたら嬉しいですね。

『TAN PEN TON』では、ソーダやポップコーンなども提供。飲食しながらショートフィルム作品に触れることができる
※画像元:https://motion-gallery.net/projects/TANPENTON
—今後、『TANPENTON』を拠点に仕掛けたい実験を教えてください。
鈴木:林君と、ワークショップみたいなことをやっても良いんじゃないかという話をしました。1日で映画をつくって、最後に皆で観られるような。で、「お前の企画おもしろいじゃん」とか「そんな方法もあったんだ」とか「雨ふっちゃった」とか……そういう体験をみんなでつくれたら面白いかもしれない。あとはショートフィルムのフルコースを食事と一緒に頂けるイベントとか。同じくBONUS TRACKに入居する『本屋B&B』さんが本にとどまらずいろいろ広げていることに近い感覚で、ここを起点にショートフィルム以外のカルチャーともつながっていくと、良い化学反応が起こる気がしています。映画だけに閉じず文化全体を俯瞰する視点を持つことがすごく大事だと思うんです。例えばミュージックビデオをつくるためにミュージックビデオばかり観ていても面白いものはできなくて、いろんな血を自分の中に入れることでアイディアが生まれてくるんです。文化もそういうものだと思うので、この小さな拠点で、いろんなものをごちゃまぜにしていきたいですね。

林:大妄想レベルの話ですけど、街中にブラウン管を置いた「ブラウン管フェス」みたいなことをやりたいですね。いろんなところにブラウン管が置いてあって、みんなで楽しむような……。
鈴木:道端で拾ったVHSを入れて観るとか、お店をまわってVHSを借りてくるとか……。逆に新しいかもね。BONUS TRACKだけじゃなくミカン下北とかも巻き込んで、横断的に。みんなが新しい作品と出会い、才能が知られて、良い循環が生まれる土壌になれたら、閉塞的な映画業界も少し風通しが良くなるかも。下北沢にいる人なら受け入れてくれるはず……。妄想が膨らみますね(笑)。こういう妄想ができるのも、下北沢だからですよね。
林:下北沢だったら、可能性0%じゃないよね?
鈴木:72%くらいはあるんじゃない?すごいイメージできた。
林:最終的な裏野望は、生産終了しているVHSとブラウン管をもう1度生産すること(笑)。その可能性を立証するためにも「ブラウン管フェス」やりたいですね!